憧れのヒューリスティック B328『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』(ダニエル・ピンク)
 ダニエル・ピンク (著)
ダニエル・ピンク (著)講談社 (2010/7/7)
今さら?と思うかもしれないけれども、これまでこの手の本にはまったく興味がなかったので仕方がない。
まずは、古典といえるような基本的なところを抑えておくべきだろうと読んでみた。
管理(Management)から自律(Autonomy)へ
本書の内容を一言で言うなら管理(Management)から自律(Autonomy)への転換だと言えるだろうか。
同様の対比として、
- 統制(Control)から信頼(Trust)へ
- 従属(Compliance)から貢献(Contribution)へ
- 外発的動機(Extrinsic motivation)から内発的動機(Intrinsic motivation)へ
- 短期的成果から長期的成長・創造性へ
とも言えるだろう。
これまでは、アメとムチによる管理(Management)がうまくいっていたし、現在でも多くの組織がマネジメントを主軸としているそうだが、なぜ転換が必要なのだろうか。
VUCA(ブーカ)
VUCAという言葉すらほとんど聞いたことがなかったくらいの経営音痴なのだけど、最近読んでいる本にはほとんど前提としてこの言葉や似た概念が出てくる。
Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった造語だそうだけれども、これらの言葉通り、変化が激しく不確実で、複雑化した先の見えない社会で生き残るのはこれまでのやり方だとうまくいかない、ということだ。
特に、不安定で小さなスタートアップのような会社では、柔軟に変化していけるかどうかが生き残る鍵となるし、そもそもリモートワークやプロジェクト型の働き方では管理には限界があり、自律と信頼を基盤にしないと機能しない。
しかし、アメとムチによる管理がなくて、果たして自律なんてことが可能なのだろうか。
モチベーション3.0の3つの要素
多くの人はそう思うだろうが、実際には「アメとムチ」による外発的な動機づけは、創造性や主体性を必要とする仕事には逆効果であることが、心理学や行動経済学の研究で明らかになっている。(とは言え、安定した報酬がベースにあるのも確か。コントロールするための報酬ではなく、自律を促すための報酬)
一時的には報酬や罰で人を動かすことができても、それは往々にして「報酬の隠された代償(コスト)」を生む。
たとえば、やりがいや好奇心から自発的に取り組んでいた行動が、「報酬がもらえるからやる」にすり替わってしまい、報酬がなくなったり外部からの圧力が強まることで、内発的なモチベーションが削がれてしまう(結果的にマイナスの効果)。そもそも人は報酬を餌にするだけでは「自律的になろう」というモードにならない気もする。
ここで思い出されるのが、アルゴリズミックとヒューリスティックという区分だ。アルゴリズミックとは、決められた手順を正確に踏めば答えにたどり着ける仕事のこと。工場のライン作業や、明確なマニュアルに基づく処理などが典型だろう。一方のヒューリスティックは、問題が複雑で答えが一つに定まらない、試行錯誤や創造的な判断を伴う仕事を指す。
これまでの「アメとムチによる管理」が有効だったのは、主にアルゴリズミックな領域においてだった。だが、今日の知識社会やVUCAの時代に求められるのは、むしろヒューリスティックな能力であり、そこでは内発的動機がなければ能力が発揮されない。
そういう視点で考えた時に、現在の環境で人を動かす力とは何か。著者はそれを 「自律(Autonomy)」「熟達(Mastery)」「目的(Purpose)」 の3つに整理する。
- 自律(Autonomy):やり方や時間を自分で選ぶ自由があるほど、人は責任感と創造性を発揮する。
- 熟達(Mastery):昨日より今日、少しでも上達しているという感覚が、努力を継続させる。
- 目的(Purpose):自分の行為がより大きな意味や社会的意義につながっていると感じることが、持続的な力になる。
つまり、外側から与えられる「管理」ではなく、内側から湧き出す「自律・熟達・目的」にこそ、変化の激しいVUCA時代を生き抜くエネルギーがある、というのが本書のメッセージだ。
まずは視点を変えてみる
とは言え、そんな状態を果たしてどうやって作ることができるのか、というのが次の疑問。
管理する側も管理される側もあまり経験せずにこれまで来たけど、管理に頼りたくなるという心境は理解できるし。
従来のように上から下へと一方的に指示を流すのではなく、メンバー一人ひとりが主体的に動き、互いに学び合いながら成長していくような仕組みづくり。そうした方向性に向けて、さまざまな理論や実践が積み重ねられつつあるのだと思うし、調べればバックデータも豊富にあるのだろう。
近年の組織論やマネジメント論は、まさにVUCA時代に適応した「自律的で創造的な組織」をどうすれば実現できるかをテーマとして発展してきているのだ、と少しづつ分かってきた気がするし、本書でもツールキットとしていくつもの提案がなされている。
とはいえ、新米管理者が簡単に実現できるとは思っていない。(本来なら、ステップを踏みながら徐々に管理者スキルを身に着けていくのだろうけれどもほとんどゼロからなので)
焦りすぎずに、少しづつ試行錯誤しながら(時に失敗しながら)感触をつかんでいくしかないと思うけれども、まず大切なのは「管理から自律へ」という大きな流れを理解し、これからの組織やチームのあり方を模索するように視点を変えることだろう。
ノウハウとか手法とか思考ツールとか、どちらかというとあんまり好きじゃなかったんだけど、まずは抽象的な理解を先行して進めて、それに対する実験、くらいの気持ちで取り組んでみようと思う。
「アルゴリズミックからヒューリスティックへ」を自分に当てはめてみるとこれは単純な二元論じゃない。みんな大好きな「守破離」だってまずは型が大切だと言っている。やみくもにヒューリスティックに走るだけではうまくいくとは限らない。(ヒューリスティックのベースは経験に基づく直感)
そう考えると、ここでの読書記録は「まずは抽象的な理解を先行して」=アルゴリズミックに型を身につけるための一歩と位置づけられそうだ。そこから現場での経験を重ねながら、自分なりのスタイルへとヒューリスティックに展開していければいい。
建築では抽象的な型を磨くことに熱中しすぎて、なかなかヒューリスティックな領域に踏み出せないんだけど、気づけばもう50。それでもまだ探求ばかりしているあたり、もう病気なんだと思う。
このテーマについてはまだ入り口に立ったばかり。だからこそ、次にどんな本や考え方に出会えるのか楽しみにしている。(どちらも探求だけで終わらないようにしなければ…)
 展覧会レポートその2 投票ランキング
展覧会レポートその2 投票ランキング 展覧会用の台をつくるなど
展覧会用の台をつくるなど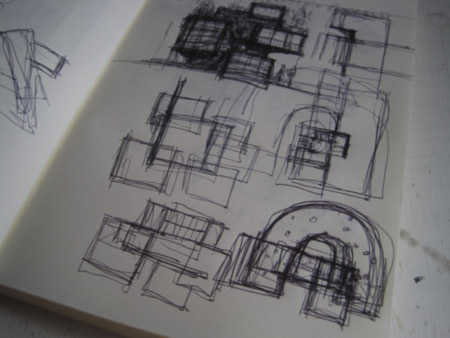 HS-24
HS-24 焦点を絞れる状況を作る B327『エンジニアのためのマネジメントキャリアパス ―テックリードからCTOまでマネジメントスキル向上ガイド』(Camille Fournier)
焦点を絞れる状況を作る B327『エンジニアのためのマネジメントキャリアパス ―テックリードからCTOまでマネジメントスキル向上ガイド』(Camille Fournier)
 出会う建築
出会う建築 動態再起論
動態再起論 環境配慮型ブランド
環境配慮型ブランド 不動産
不動産