5本の指と4つの谷
今日、某建物のお別れ見学会が開かれていた。
奇しくも同日、私はすぐ近くで、テンダーさんの某組合員の方たちへのシステム思考ワークショップに参加していた。
ちょっと感じたことを書いておきたい。
某建物はなぜ残せなかったのか
某建物はなぜ残せなかったのか。
そこには様々な要因があり、それらが行き着いた結果として残せなかったという現実がある。
システム思考的には、そこに悪者がいる、とは考えない。そういうシステムがあり、そういう結果があった。まず、それを認識する。
某組合の(少なくともこの会に参加された)方々は勉強熱心で、使命感があり、善意に満ちた、大人としての責任に向き合おうとしている人たちであることは容易に感じ取れた。
それでも、建物は残らなかった。
なぜか。
私の見える景色の中で、その要因は何だと言えるだろうか。
それを私は考えてきたはずなのに、その時ちゃんと言葉にできなかった。そのことを後悔したのでここでもう一度考えてみよう。
建築の意味と価値
その要因の一つが、私たちが建築の意味や価値を文化として根付くところまで共有できていないことにあるだろう。
もうだいぶ前になるけれども「出会う建築」で、私はこう書き始めた。
今、目の前にある、その建物。
その建物に、どんな意味や価値があるだろうか。また、それを語る言葉を持っているだろうか。
多くの建築家と呼ばれる人々は、建物を設計する際に、または、ある建物に意味や価値を見出した時に、あるいはその建物が意味や価値を持つことを期待して、その建物のことをわざわざ「建物」ではなく「建築」と呼んだりする。そして、その建築の意味や価値をどこまでも追い求める。
だけども、建築家たちが切磋琢磨して追い求める、その建築の意味や価値は、多くの人々に認められていると言えるだろうか。
『良いものをつくれば、それは必ず人々に伝わるはずだ。』
もしかしたら建築家はこう言うかもしれない。それはある面で正しいと思う。だけども、やっぱり多くの人々はその建物を語る言葉を持っていないし、その素晴らしさに気付くことなく通り過ぎてしまう。
まちの景観や、歴史的建物の保存・活用などが、限られた人たちだけの話題となってしまい、なかなか有益な議論や結果に結びつかない、ということの根底には、殆どの人の中には、建築という概念、または建築の意味や価値を語るための言葉が存在していない、ということがあると思う。
建築は、私達の生活する環境をかたちづくるものであって、生きていくうえで大切な要素だと思うのだけど、ほとんど人に語られてこなかった。まずは、誰でもが建築の意味や価値について考えられるような、言葉や状況を生み出す必要があるんじゃないだろうか。(〇 はじめに – オノケン│太田則宏建築事務所)
そう、例えばこの建物を残すことに何の意味や価値があるのか。
それをきちんと説明するための言葉や状況があまりに不足している。
それが、やはり残せなかったという結論に行き着いた一つの要因である、と考えることにそう無理はないだろう。
5本の指と4つの谷
ある、リノベーションの大家の言葉に「あなたでなければ・いまでなければ・ここでなければ」というものがある。
あなた(私)、いま、ここ、という視点にきちんと向き合うことが街の価値を高めることにつながる。リノベーションの極意を簡潔に表現するまさに名言である。
一方、異なる文脈で考えると、私、いま、ここ、という視点にとらわれることが、環境問題などのさまざまな問題を引き起こしてもいる。
テンダーさんは、ワークショップの冒頭、片手の5本の指を開いて、これが示す数を問うた。
当然、皆5だと答える。
しかしテンダーさんは、5本の指だけでなく、それらの間にある4つの谷、つまり指と指との関係性に目を向けることがシステム思考の入口だという。(厳密な言葉遣いは覚えていないので、以降、私の理解による言葉)
5本の指だけを見ているだけでは個別の事象を見ているにすぎないし、そこからシステムは浮かび上がってはこない。
それらの間にある関係性に目を向けることで初めて全体がシステムとして浮かび上がり、それらの事象のシステム的な意味や価値も見えてくる。
わたし、いま、ここ、というのは3本の指、事象に過ぎないが、そうでないもの、例えば地球の反対側の貧しい国に住む誰かや、過去の出来事、未来の子どもたちといった異なる無数の指がある。
しかし、多くの場合、わたし、いま、ここ、とそれらの間に関係性があることは覆い隠されて見えなくなっていて、ほとんど存在しないことと同じだ。
(それをインセクトでは「分断と転嫁の思想」と呼んだ)
なぜ今、この話を持ち出したか。
それは、建築が、5本の指の間の4つの谷を表現し、指と指とをつなぐ役割を担えると考えるからである。
建築は時を超えた出会いを可能にする
それについては「出会う建築」に書いたので全ては書かないが、例えば、建築は時を超えた出会いを可能にする。
建築は今という指と過去という指の間の谷を実在するものとして表現し、つなぐことができる貴重な存在である。これほど長期間に渡り存在し続けることのできるものは、他にそうそうないし、これほど多くの情報(生活や技術、思想や哲学など)を伝える存在もそうない。
前に書いたように出会いは、個人や、時間、空間などさまざまなものを超える。
言い換えると、(私、いま、ここで)を超える。私はこれを建物が建築になるための一つの要件だと考えているのだけれども、(私、いま、ここで)を超えるということは、それによって(私、いま、ここで)を支えることでもある。関係性を持つこと、相対的であること、すなわち他者との出会いががなければ、(私、いま、ここで)にも出会えない(意味や価値が見いだせない)のだ。
(私、いま、ここで)を超えて、皆とともにいること、そこに住んでいること、歴史の中にいること、文化を共有していること。それらは、いずれも他者との出会いの中にあってはじめて生まれるものである。(二-十五 社会・歴史・文化―時間と空間を超えて – オノケン│太田則宏建築事務所)
新しい建物のみで全てが埋め尽くされた街や世界に住んでいることを想像してみて欲しい。
そこには、30年以上前に建てられた建物は存在しない。
(既にかなりそうなりつつあるけれども)そこで育つ子どもたちは、果たして過去や未来とのつながりを感じることができるだろうか。
頭ではなく、実感をもって歴史とのつながりを体得することができるだろうか。
そうして育った大人が未来の子どもたちを思った生活を選択できるだろうか。
テンダーさんは講座の中で、2000年間培われてきた過去の技術の中に普遍的な答えがある、というようなことを言われていて、私も少しづつそれが分かってきた。
しかし、そうして育った子どもにこの言葉が伝わるだろうか。そもそも、過去とのつながりが絶たれた世界では、その普遍性に気づくことができたのだろうか。過去とのつながりがかろうじて残っているからこそ、今のテンダーさんが生まれたのではないだろうか。
過去との出会いを可能にする建築が豊富に存在するのであれば、それが失われることにはそれほどの意味はないかもしれない。
しかし、そうではない現実の中では、過去とのつながりの可能性の一つが失われた、というのは大きな喪失の一つであり、歯止めをかけない限りは今後も失われ続けることになる。
単に一つの建物が失われたのではなく、過去と現代をつなぐ一つの可能性も同時に失われたのだ。
そして、一度壊した建築はニ度と元に戻ることはない。
それは、しかたがないか否かとは関係なく、一つの事象として何かの結論に向けてシステムに影響を与える続けることになる。
私は、今日どう表現するべきだったのだろうか。
「特定の誰かが悪いわけではないと思います。でも、5本の指の間の谷のいくばくかが永久に失われることになったことは間違いありません。」
これが当たり前に表現され、共有されていないことを今の現実として受け止める必要がある。
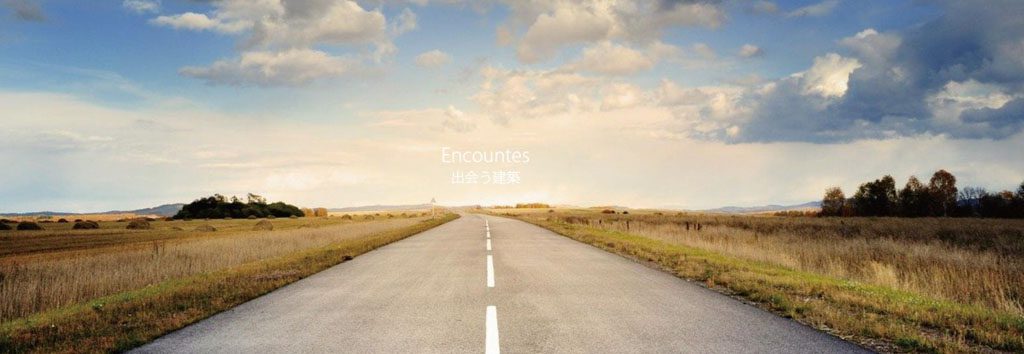 二-十五 社会・歴史・文化―時間と空間を超えて
二-十五 社会・歴史・文化―時間と空間を超えて Deliciousness / Encounters
Deliciousness / Encounters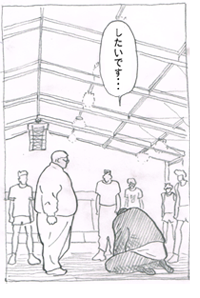 安西先生・・・・・園舎の設計が
安西先生・・・・・園舎の設計が
 出会う建築
出会う建築 動態再起論
動態再起論 環境配慮型ブランド
環境配慮型ブランド 不動産
不動産